畑(田んぼ)に家を建てたいんだけど,どうしたらいいんだろう?
費用はどのくらいかかるのかな?
そんな悩みをお持ちの方はいませんか?
はい,私がそうでした。
こんにちは,ちゃんぴーです♪
私が家づくりをしていく上でまず考えたのが,「どこに」家を建てるのか。利便のいい市街地か,学校が近い場所か,景色がいい場所か,のびのび育てられる田舎か,どこがいいんだろうと悩みました。
結果,実家が所有している畑をもらい,自然豊かな田舎に建てることになりました。周りにコンビニやスーパーはなく,生活に車が必須な少し不便な場所ですが,なぜそこにしたのか。
それは,市街地の土地を買うよりも,畑を宅地にした方が圧倒的に安く,建物にお金をかけられるし,広い土地でのびのびできると思ったからです。利便性を捨てて,コストと自由を取りました。
私が住む地域では,50坪前後の分譲地でだいたい2000万円~3000万円といったところです。それに建物の費用を合わせると,ざっと5000万円はかかります。土地探しをする前は「貯金はないけど,3500万円ぐらいで建てたいな♪」とか考えていました。そして,近くの土地の金額を見て絶望。土地って高い!
家づくりにおいて,土地探しは非常に重要です。家自体の快適さは工夫次第で何とかなりますが,場所はどうにもなりません。毎日仕事や学校,買い物などの生活を過ごしてみて,「なんだか生活が大変だな」と思っても,もう変えることはできないのです。
自分たちのライフスタイルに合った土地,予算に合う土地を後悔なく見つけるためにも,しっかり情報収集をしていくことをオススメします。
今回は,畑を宅地にするためにどんなことをしたのか,かかった費用などを紹介したいと思います。もしこれから田舎に家を建てたいと思っている方がいれば,参考になれば幸いです。
畑(田んぼ)の番地・地目・面積の確認
まず行なったのが,畑(田んぼ)の番地・地目・面積の確認です。土地の所有者である私のおじいちゃんから,毎年4月に送られてくる固定資産税の課税証明書を見せてもらいました。
そこで驚きの事実。いつも野菜を育てていた畑だと思っていた場所は,実は「田」だったのです。昔はそこで米を作っていたけど,野菜作りのために畑に変えたらしい。いや,地目変えなくていいの?(笑)
なので,畑(田んぼ←ややこしいのでもう畑ということにします)の端の方には,田んぼの名残である水口(用水路から水を引く穴)と排水口がありました。この穴が後々頭を悩ませることになるとは,この時は知る由もなかったのです・・・
ちなみに畑の面積は497㎡!(約150坪)
「わーい。広い家と庭ができる~」とのんきな私は思いました。しかしこの土地の広さが後々私を苦しませることになるとは,この時は知る由もなかったのです・・・
畑の所有者の変更手続き
農地に家を建てるためには,農地法という法律が出てきます。農地の地目や所有権を移動するには許可を得なければなりません。
3条…地目はそのままで,所有権を移動
4条…所有者はそのままで,地目を変更(転用)
5条…所有権を移動し,地目も転用する
田舎に家づくりをされる方はほとんどが上の農地法5条や4条,いわゆる農地転用を行います。しかし今回私は農地法3条を手続きしました。
農地転用後は地目が宅地になるので,1年以内に住宅を建築しなければいけない決まりがあります。本来ならすぐに家を着工するはずなので,5条でも大丈夫です。
私の場合は,夫の仕事や子どもの進学の都合ですぐに着工ができなさそうだったので,3条で土地の所有権だけでも先に変更することにしました。
農地法3条の許可申請の手順
- 司法書士さんを紹介してもらう
- 3条許可申請の書類作成(費用削減のため自分でやりました)
- 農業委員会に書類を提出しに行く
- 農業委員会から農地法3条が許可された通知が届く
- 司法書士さんに土地の贈与登記手続きを依頼する
- 土地の登記が完了し,登記簿謄本が自宅に届く
農地法3条許可申請にかかった費用
司法書士さんに依頼した費用がかかっています。また本来なら,下記の費用に3条許可申請の書類作成費用が追加されます(おそらく+5万円ぐらい)。依頼する事務所によっても価格は変動するので,参考程度にお考え下さい。
| 所有権移転(贈与) | 60,000円 |
| その他費用 | 5,000円 |
| 消費税(10%) | 6,500円 |
| 合計 | 71,500円 |
確定測量(現況測量・境界確定)の実施
次に行うのが確定測量です。昔ながらの農地は隣地との境界もあいまいだったり,実際に測量をしてみると面積が違ったりしています。それを明確にするのが確定測量となります。
ハウスメーカーや工務店は,まずその土地の敷地調査を行います。境界杭を見ながら改めて測量することで現況図を作成し,それをもとに間取りなどを考えていきます。
つまり確定測量を行わないと,先に進めないのです!
早速,ちゃんぴーも確定測量を依頼しました。
確定測量の手順
- 土地家屋調査士さんを紹介してもらう
- 測量の実施
- 隣地の方と立ち会って境界の確認
- 確定測量図の完成
- 登記申請をしてもらう
越境が発覚
主な流れは上記のようになります。しかし,今回は問題が発覚しました。お隣さんの車庫が私の土地に越境していたのです。
このような場合の対処として調査士さんから2つ提案されました。
①車庫を壊してもらう
②土地を分筆して,一部譲与する
お隣さんは実家の両親とも仲が良く,なるべくトラブルは避けたいと思っていました。というより,①はあんまりじゃない?
土地も十分に余っていたので②を即決。土地の分筆手続きと費用が追加されることになりました。
お隣さんが「分筆費用を払います」と言ってくださったのですが,断りました。越境しているのはあちらなので,それが普通みたいです。ただ本当にお隣さんとは仲良くしていきたいので,今回はこちらで負担することを選びました。
隣地との境界問題は結構ざらにあるようです。後々のトラブルを未然に防ぐためにも確定測量は大切なんだなと思いました。
確定測量にかかった費用
土地家屋調査士さんに依頼した費用がかかっています。確定測量は土地の広さによって費用が変わります。今回は150坪での計算になっています。依頼する事務所や,土地の状況によって価格は変動するので,参考程度にお考え下さい。
| 現況測量 | 100,000円 |
| 境界確定 | 370,000円 |
| 諸費用 | 60,000円 |
| 分筆登記 | 80,000円 |
| 消費税(10%) | 61,000円 |
| 合計 | 671,000円 |
結論:確定測量の費用はかなり高い!払い方にも注意
ここまでお読みいただきありがとうございます。今回は農地法3条の許可申請と確定測量の手順や費用について説明しました。
この後にも農地法5条の申請や宅地造成などがあるのですが,長くなりそうなので記事を分けることにしました。
土地の整備が終わっている分譲地と違って,農地を宅地に変えるのにはどうしても時間や手間がかかります。最後にもう一つ注意するならば,今回かかっている費用約75万円は自己負担ということです。
土地の造成工事とは別とのことで,住宅ローンに組み込んでもらえなかったのです。今になって思うと,つなぎ融資など別の方法があったのかもしれません。そのときはかなりの出費に頭を悩ませました。
もし確定測量を行うときは,かかる費用の払い方を事前に確認しておくことをおすすめします。
以上,ちゃんぴーでした。
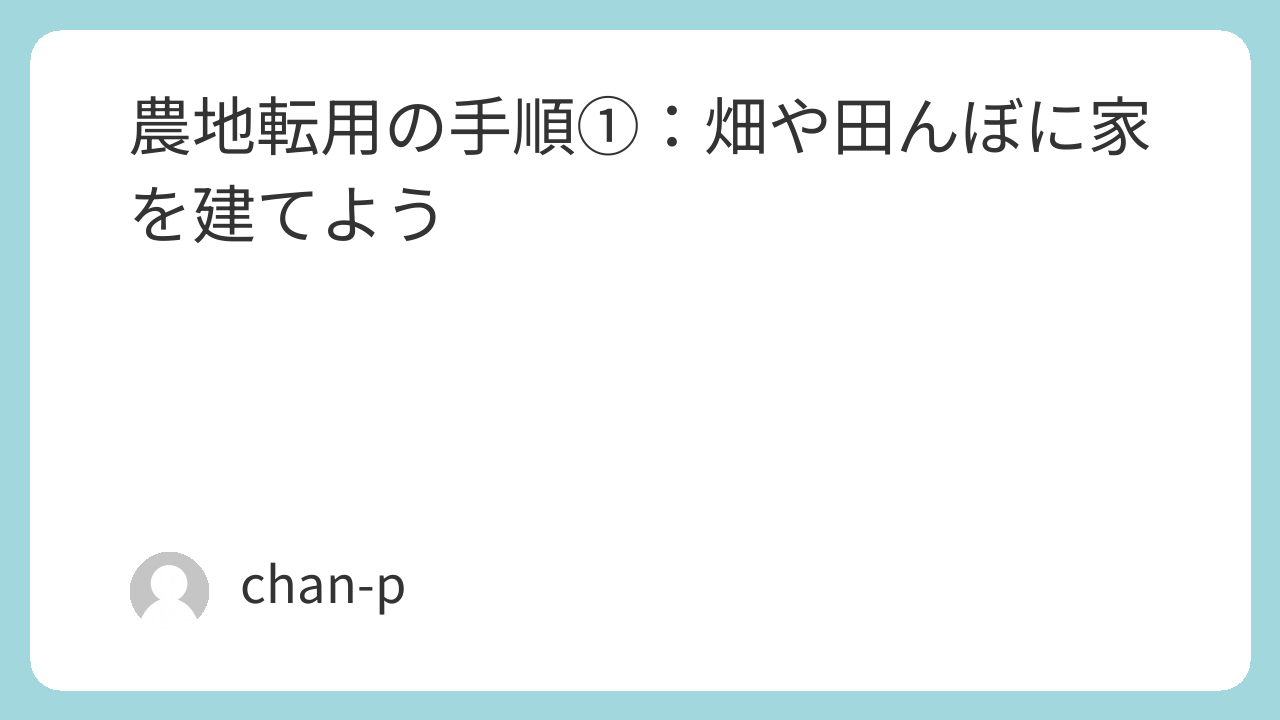
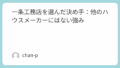
コメント